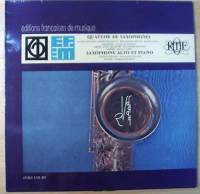
2002年
| 2月28日 |
2月は年度の替わりを控えて忙しい。それでなくても忙しいのに熱を出して寝込んでたり、やっと復活したと思ったら今度は重度の肩凝りにやられて、パソコン作業に堪えられずすっかり更新が滞っている。楽しみにしている皆様ごめんなさい。そういえば去年の今頃もこんな感じだったな。レントゲンを撮ってみたら、X線も通さないほど肩の筋肉の凝りが激しかったのだった(ホントかいな?)。
銀座の王子ホールで、大城正司さんのリサイタルを聴く。
演奏が良かったのはともかくとして、客席の「濃さ」はなかなか壮観なものがありました。左を見るとK井先生(先週リサイタルだったのだが、かなりお痩せになった様子。マスランカに精気を吸い取られたか)、後ろを振り向くと某アルモのM雪氏、右を見るとなんと、あのナベサダ氏が野中貿易の専務と並んで座っている。(ちなみにその前列には当直明けのとめちゃん氏の姿が。)300席の小ホールだけに、そんなに広くないロビーに休憩時間に出てみると、あっちにもこっちにも、あっ、あの人が!という感じだった。
終演後はホールの目の前の「影丸」という店でラーメンを食う。ある人に教わったのだが、なかなか美味しい。しかも安い(600円でライス付き、餃子が200円。銀座ですよ)。
YahooオークションでデスロジェJacques Desloges(Sax)のLPを落札、手元に届いた。A面はカルテット(ブーニョの『小品』、ピショローの『ラフレシア』、ロジェ・カルメルのロンド)、B面はデスロジェのソロでケクランのエチュード抜粋(1、2、3、6、8、9、10、11、13、15)。このケクランがなかなか、いいです。
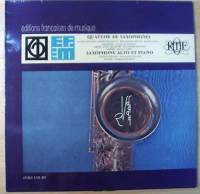
木下さん(当日記にもよく登場する知り合いのレコードコレクター)も新たに昔のLPを入手されたそうで、聴かせて下さった。ギャルド・レピュブリケーヌ・サクソフォン四重奏団の、私は見たことのないレコードだった。A.Lemeland、R.Nicolas、M.Bagot、P.Sciortino、J.Bernard の作品を収録。曲も知らないものばかりだ。ショルティーノ(『異教徒の踊り』の作曲者)はかろうじて知っていたが、この Agogik という作品は初耳だ。うむ、世の中はまだまだ広いなあ。
| 2月17日 |
今日はいろいろと予定が重なった日だったが、昼は都響の東京芸術劇場シリーズを聴きに出る。ドヴォルザークの特集。スラヴ舞曲の第5、6、8番、ヴァイオリン協奏曲(ソロ:徳永二男)、休憩後は交響曲第8番。
指揮は引き続きローレンス・フォスターだったが、どうも指揮者の方向性とオーケストラのそれが微妙にくい違っているようなところがあり、こういうよく知っている名曲プロの場合はそれがなんとなく音に現れているのが聞き取れる。勿論、表向きは破綻をきたさないようまとめていたのはさすがプロというか、曲の終わりの「決め」など見事なもので、終演後の会場は大いに沸いたのだが。(曲の「終わり方」の重要性というのは、昔須川さんのレッスンでしつこく言われた記憶がある。)
アンコールにスラヴ舞曲の第10番(作品72-2)。
| 2月16日 |
「なめら〜か」練習。事前の欠席連絡は2名のみだったので人が集まるかと思いきや、当日ダウンした人間が4人(練習終了時までに連絡してきた人は1人だけ。練習室の目の前まで来た人はいたようだが(笑))、早退2人、遅れて来ると言っていたが結局来なかった1人、行方不明1人で、最終的出席者は4人でした。はははは、どこが「ラージアンサンブル」なんだかねえ。分母が40人や50人の楽団だったら一度に10人くらい休むのはまぁ当り前にあることだが、総勢14人のアンサンブル団体でそれをやられるとちょっと困っちゃうぞ。
結局、皆さん、「自分が居ないこと」が楽団全体に及ぼす影響についての認識が薄いんだね。だからいくら体調が悪いからとはいえ、連絡もなしに休んだりということが平気で出来る訳だ。私には理解し難いことだが。
解散後はサントリーホールへ移動、東京フィル定期を聴く。
指揮は小松長生。私なんかと同世代の若手指揮者だが、東大美学科からイーストマン音校の指揮科に進んだ異色の経歴の持ち主だ。何年か前に日本フィルで、伊福部のSF交響ファンタジー、コープランドのロデオとエル・サロン・メヒコ、ウェストサイドよりシンフォニックダンス、というオケが壊れそうなプログラムの演奏会を聴いたことがある。
細川作品は初めて聴いた。聴いたことのあるこの人の他のいくつかの作品のスタティックな印象とはちょっと違う、ヨーロッパ風にドラマティックな音楽だった。作曲者臨席。
シュトラウスのOb協は実は大好きな曲で、演奏会プログラムに載った時は極力聴くようにしている作品のひとつ。特大編成の前後の曲にはさまれて、爽やかさが引き立っていた。シェレンベルガー、さすが上手いです。
チャイコフスキーの、特に5番というのはいやがおうでも盛り上がる曲で、実際盛り上がったけれど、ちょっと予定調和、という感じもある。この感じから脱却するのはそれはそれで難しいのだろうが。
アンコールにラフマニノフの『夕べの祈り』(原曲は合唱曲)の弦楽合奏版。しっとりと終わった。
| 2月15日 |
カザルスホール・アマチュア室内楽フェスティバル(ACF)初日。ネット上でちょっとだけ交流のある浜松のサクソフォンカルテット(ゼフィールSax.Q)がトリで出場するのを知っていたので、当日券で入る。Niftyのネット仲間で昨年出場したアンサンブル・カテナリスの面々も全員聴きに来ていた。
3番めの団体から聴く。チェロ九重奏、リコーダークワイア、弦楽五重奏、アコーディオン八重奏。演奏形態もレベルも千差万別だが、少なくとも半端じゃない入れ込みようで活動を続けてエントリーしてきている団体ばかりだなあと思われる。実はわれらが「なめら〜か」も今回応募して、二次選出までは行ったものの出場には至らなかったのだが、我々が出るのはまだ10年早いという感じがなくもない。もっとも、今のカザルスホールを取り巻く状況を考えると、10年後なんてどうなってるか分からんが。
ゼフィールの演奏は、メンデルスゾーンの『プレリュードとフーガop.35-5』。コンパクトにまとまった見事な演奏だった。
カザルスホールの音響は、以前と比べて(舞台上にオルガンが付いてからだと思うのだが)、良く言えば引き締まり、悪く言うと鳴らなくなった。10年前私たちが乗った頃は、サクソフォンだとわんわんに響いてしまってウルサかった記憶があるのだが、今回は全然そうは思わなかった。それでも一流のホールであることは変わりないのだが、なんだか「普通に良い」ホールになっちゃったなあ、というか。
ギュンター・ヴァントが亡くなったそうだ。90歳。(朝日新聞の見出しの「バント」には力が抜けた…)
実は私、あんまりこの人を真面目に聴いたことがなかったりして、それより日本フィルのホルン首席奏者の平塚さんがオケの九州演奏旅行中に急逝されたというニュースのほうが私には衝撃的だった。33歳(若い!)。数年前にコバケンの指揮で聴いたマーラー5番の入魂のソロを思い出す。…
| 2月14日 |
N響定期を聴く(NHKホール)。
指揮シャルル・デュトワ、ヴァイオリン諏訪内晶子という豪華顔合わせ。しかもメインプロが『幻想』。いつもだったらガラガラのAシリーズ1日めだけど、今日はさすがの大入り。それでも(開演直前に飛び込んだけど)1520円で自由席当日券がいくらでも買えるN響はステキです。
演奏も久々にデュトワの本領発揮という感じだった。武満の響きがラヴェルの曲のように聞こえる。『幻想』も、エレガントな響きを基本にしながら迫力や勢いも充分に!あり、楽譜上のアクセントのグロテスクなまでの強調とかクリティカルな興味も欠かさない。こういう多面性がデュトワの万人に受け入れられる人気のもとなんだろうな。終演後の客席はすごい盛り上がりだった。第1楽章提示部を楽譜どおり反復していたのには驚いた。実演で聴いたのは初めてだ。
諏訪内嬢のプロコフィエフは、すいません、途中でちょっと眠ってしまったのでノーコメント。どうもプロコのVn協って私には鬼門で、百発百中で眠ってしまうのだった。
先日、プロコフィエフの『キージェ中尉』を聴いて思い出したことがある。
キングレコードから「N響伝説のライヴ」という、N響定期公演のライヴ録音のCDシリーズが発売されていて、その中にコンドラシン指揮のプロコ5番と『キージェ』(1980年1月録音)という組み合わせのがあるのだが、この『キージェ』でテナーサクソフォンを吹いているのはたしか若き日の冨岡和男氏だったと思う。演奏された当時、テレビで観た記憶がある。なにしろ20年以上も前のことなので(ちょうど自分が高校を卒業して大学に上がる頃)、記憶違いだったらご容赦を。
終演後は、たまたま仕事で上京してきている高知のSax吹きの知り合いOさんの迎撃会を催す。出席者4名。N響を一緒に聴いた後だったので、地方公演と明らかに違う定期の演奏水準にびっくり仰天していた様子だった。山手線の向こう側の「千」という小さな飲み屋で、0時近くまで騒いだ。土佐弁全開のお喋りが楽しかった。なんだか本当に坂本龍馬と話しているような感じだったぞ(^o^)。
| 2月8日 |
都響第544回定期を聴く(サントリーホール)。
指揮はローレンス・フォスター。盛り沢山で非常に面白いプログラムだった。中でもアーティー・ショウ(アメリカの有名なバンドリーダー&クラリネット奏者)の協奏曲というのが、8分弱の小品ながら「ストリングス付きビッグバンド」の編成で(金管+サックス4+弦+ピアノ、ドラムス、エレキギター、エレキベース)、サントリーホールが即席ライブハウスになったような雰囲気は最高だった。ラッパやサックス群(メンバーは見たところ田中靖人、大城正司、新井靖志、大津立史という4人)はスタンドソロもあったし。ちなみにエレキベースをオーケストラの首席コントラバス奏者が弾くとのことで驚いたが、実際に弾いていたのはヤマハのサイレントベースだった。なるほど。
クラリネットのシャロン・カムのソロも、2曲とも暗譜で素晴らしいものだった。今日の2曲を含むCDを出したばかりとのことで、ロビーで売っているかと思って見に行ったら既に品切れだった。コープランドの協奏曲も面白い曲だ。以前1回聴いたことがあるはずだが、その時はあまり印象に残らなかった。4月に紀尾井シンフォニエッタがスタンリー・ドラッカーのソロで演奏するらしいので聴きに行こうかな。
他の曲も管楽器好きにとっては興味深いものばかりだったが、終わって印象に残っているのはむしろ、繊細でしかも一糸乱れない弦楽器群の健闘だったかもしれない。それにしても3日かそこらの練習で、この曲目をこの水準に仕上げるプロというのはすごいよなあ…
| 2月6日 |
村田健司(バリトン・レジェ)サロン・ドゥ・サロン第36回公演を聴く(原宿・アコスタディオ)。今回はラヴェルの夕べ。
会場であるビルの地下2階の小さなスタジオに入ると、いつものように村田さん自身のお出迎えと駆けつけ一杯のワイン。クローク係まで本人が買って出ていた。演奏会というより、ホスト村田さんのパーティに呼ばれたような気分だ。曲目は以下の通り。
ラヴェルの歌曲だけで1晩というのは滅多にないことで、貴重な機会だったが、感想は「いや〜、ラヴェルでした、」ってところ。実に面白い。諧謔と皮肉、仕掛けと謎に満ちたラヴェルの相貌みたいなものが、オーケストラ曲やピアノ曲よりよほど直接的に見えてくる、ような気がする。「言葉」って偉大だな、と思った。
休憩時間には、村田さん自身が正月にフランスから持ち帰ってきたユーロ紙幣を見せて回っていた。新しいお札というのはどんなものであれオモチャっぽく見えるなあ。単色に近い明るいデザインと貼りつけてあるホログラムのおかげで、なんだかギフト券のようにも見える。ちなみにこんな感じ。
家に帰ってから、思い立って今日のプログラムになかったラヴェルの1曲、ジェシー・ノーマンの歌う『マダガスカル島民の歌』を聴く。ブーレーズ指揮のソニー盤。…うーむ、声はともかく、このフランス語の発音はどうにかならんもんだろうか(^_^;。まあ、仕方ないか。
先日参加表明をした「淡路島サクソフォンフェスティバル2002」の資料&楽譜が届いていた。メインプロは『1812年』。うわ〜っ、なんなんだこの譜面は。ちょっとびっくり。
4月27日・東京農大オーケストラ定期演奏会の『アルルの女』のエキストラの依頼を受けた。「★ベー◎」を除けば久々のオケソロで、楽しみ。